netto(ねっと)で訪問している方の中には、食事を作ったあと食事をご一緒することもあります。
一人分を作るのが難しいとか、そういった理由もあるのですが、どちらかというと食べるという行為自体について私たちなりに考えていることがあるからというのが理由です。
先日、ケアマネさんが訪問した際に、「プロテインがおすすめです、最近のものは栄養バランスが整っていますし、食事はレトルトの味噌汁などにして、プロテインも飲めば栄養素は摂れますし、食材を買ったり、余らせたりすることもないので逆に経済的で困り事も少なくなりますよ」という内容を言われて納得したとご家族から報告を受けました。
確かにそうかもしれませんが、強い違和感を感じたので、こちらが考えていることをご家族に伝えさせてもらいました。
栄養素を摂るというのは食事の一要素に過ぎない、と言うのは誰しも共感してもらえると思います。
身体は世界と関わることで意味を紡いでいくことができます。
身体は機械のような単なる物質ではなく、世界と関わり、意味を生成する主体であると言ったのはメルロ=ポンティ(身体性について考えるうえで私の好きな哲学者です)ですが、身体が持つ多様な感覚や食を通じて世界と関わる豊かさが失われることが最も懸念されることだと思うのです。
高齢者だから仕方ないって思想的には克服すべきでは?
まず何よりも初めにこのことについて考える必要があります。たとえ毎日でなかったとしても味噌汁とプロテインで済ますという生活を、あなただったら選択するでしょうか?
自分だったら選択しないような状況を「仕方ない」とする思想は、対象者が社会に包摂されている状態を目指すこととは対極にあります。
対象者の社会とのつながりを失わせる方向の思想(社会的排除Social Exclusion)である危険性をはらんでいるということに危うさを感じるべきではないかと思います。
とはいえ最近の完全食ブームのことを考えると、自らそう言った環境を望んでいる人も多くなっていそうですね。それはまた、世界がデータ化するような感覚があり興味深いです。
「私」という主体の希薄化
メルロ=ポンティは、身体が世界を「志向」し、意味を付与することで初めて世界が立ち現れると考えました。もしこの能力が失われれば、「私」という主体が世界とどのように関わり、何を経験しているのか、その認識自体が曖昧になり、自身の存在意義すら見失う可能性があります。
食事という行為にはいろいろなプロセスがあると思いますが、過去の食の経験(あの時の美味しさ、家族との楽しい食事など)が呼び起こされ、「あれを食べたい」「こんな味が欲しい」という具体的な期待が形作られることは身体が世界に開かれている状態だと言えると思います。それを失ってしまうことは世界を閉ざす方向に舵を切ることではないでしょうか?
食べ物の背後にある物語の受容
誰かが作ってくれた料理、生産者の顔が見える食材、旬の食材など、食べ物には必ず物語が宿っています。これらの物語を身体で受け止めることは、単なる物質ではなく、歴史、文化、そして他者の労力や愛情といった意味を享受する行為です。
そこには必ず他者や世界との関係性があり、それを感じ、受け止め、社会とつながるという行為と言えますよね。
誰かと会ったり話をするだけが関わりのすべてでは無いと思うのです。
「メバルの美味しい季節だね」
「〇〇さんがそら豆持ってきてくれたよ」
「今年は雨が多いからトマトの出来がイマイチだね」
という思考を通しても世界と深く関わっていくことができるのではないかと思いますし、そのように感じてもらえるような関わりを食事の時間を共にすることで醸成していけるのではないかと考えています。
食材との身体的・感覚的対話(世界の把握と意味の受容)
あとは単純に五感を通じた身体と世界との対話ということは重要なポイントです。
食材の持つ生命力、季節感、調理方法、味わいはもちろん、香り、舌触り、温度、歯応えなど多様な感覚が複雑に絡み合って「味」として世界が立ち上がっていくのだと思います。
また、そういった感覚的対話はこれまでの経験や期待と照らし合わせながら、記憶と結びつき、その食べ物が持つ「豊かな意味」を解釈しリプレイする行為だと言えるのではないでしょうか?
「小さい頃よく食べた」
「お袋の味」
「子どもが好きだった」
「夫がたまに作ってくれた」
というような記憶を辿ることは、回想療法にもつながるその人にとっての意味を深めることだと言えそうです。
世界との関わりを閉ざしていくことは主体性を失っていくことだと思います。
人間は自律的であることで自由と責任を持つことができるのではないでしょうか?
もし人間が「世界と関わり意味を生成する」能力を失ってしまったとしたら、私たちは単に栄養を摂取し、生命を維持するだけの、いわば「生きた機械」になってしまうでしょう。それは、喜びや悲しみといった感情、創造性、他者との深い絆、そして自由といった、人間を人間たらしめる最も大切な要素を失うことを意味します。
現代社会が直面している効率性や合理性の追求にともすれば流されてしまいがちですが、少し立ち止まって食という観点からも考えてみて、日々の関わりの中で対象者がより世界と主体的に関わることができるようにケアの視点を考え続けることは大切だと思うのです。
一緒に食べると楽しいですしね。
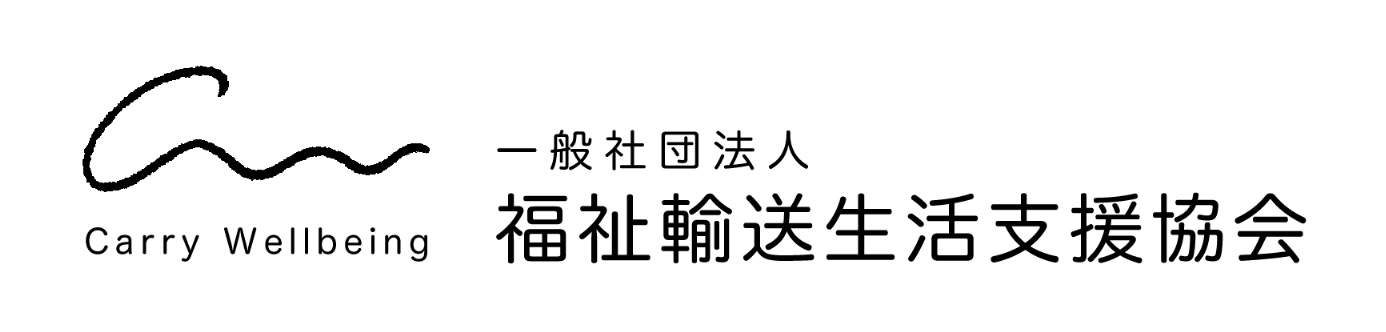
コメント